【東概011・012】生理物質『気』の特徴・作用・病理【国試対策用まとめ】
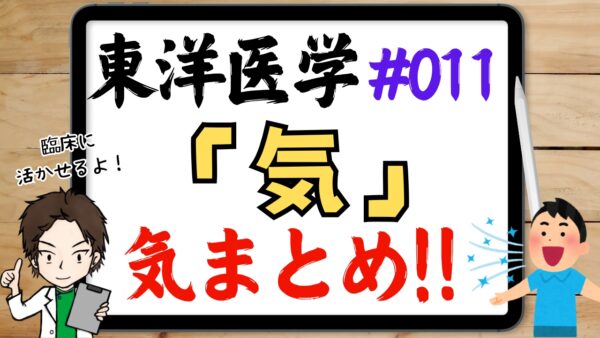
「気」とは?【全体像まとめ】
気の種類と働き
気の作用とは?【5つの働き】
準備中・・・。
① 推動作用(すいどうさよう)
成長・発育・臓腑の活動・血や津液の循環など、生命活動全体を推し進める力です。
気がなければ、身体は「エンジンがかからない車」のようになります。
② 温煦作用(おんくさよう)
臓腑や体を温め、体温を一定に保つ働き。衛気・原気・腎気と深く関係します。
この力が弱まると、冷え性・手足の冷感・代謝低下が起こります。
③ 固摂作用(こせつさよう)
体内の精・血・津液を正常な位置にとどめる働き。営気・衛気・脾気・腎気が関与します。
鼻血・下痢・尿漏れ・多汗などは、この固摂の力が弱ったサインです。
④ 防御作用(ぼうぎょさよう)
外邪(風・寒・湿など)の侵入を防ぎ、体表を守る働き。衛気が主役。
免疫のような役割で、弱まると風邪をひきやすくなります。
⑤ 気化作用(きかさよう)
体内の物質を別のものに転化させる働き。新陳代謝そのものを意味します。
例:飲食物 → 精 → 気・血・津液 → 汗・尿などへの変化。
イメージ的には「気化作用=工場」。原料(飲食物)を製品(精・血・津液)に変えるプロセスを担います。
気の異常(虚・滞・逆)
- 気虚:元気がない・倦怠・息切れ・自汗(エネルギー不足)
- 気滞:イライラ・脹痛・胸や腹の張り(気の流れが滞る)
- 気逆:のぼせ・咳・嘔吐・頭痛(気の流れが上に逆行)
気は“流れてナンボ”。止まると不調、逆行すると症状。まるで渋滞した高速道路のようですね。
気のまとめPDF【無料ダウンロード】
気の作用まとめPDF【無料ダウンロード】
国家試験・臨床どちらでも使えるよう、図表とイラストを交えて整理しました。印刷して手元で復習しましょう。
 ホネ美
ホネ美動画のグッドボタン約束やで!YouTube広めてな!
さいごに
「気」は東洋医学のすべての基礎です。精・血・津液・神のバランスを支える中心軸でもあります。
この概念を掴めると、経絡・臓腑・診断・治療が一気に繋がります。
 マッチ
マッチでは、素敵なあはきライフを!
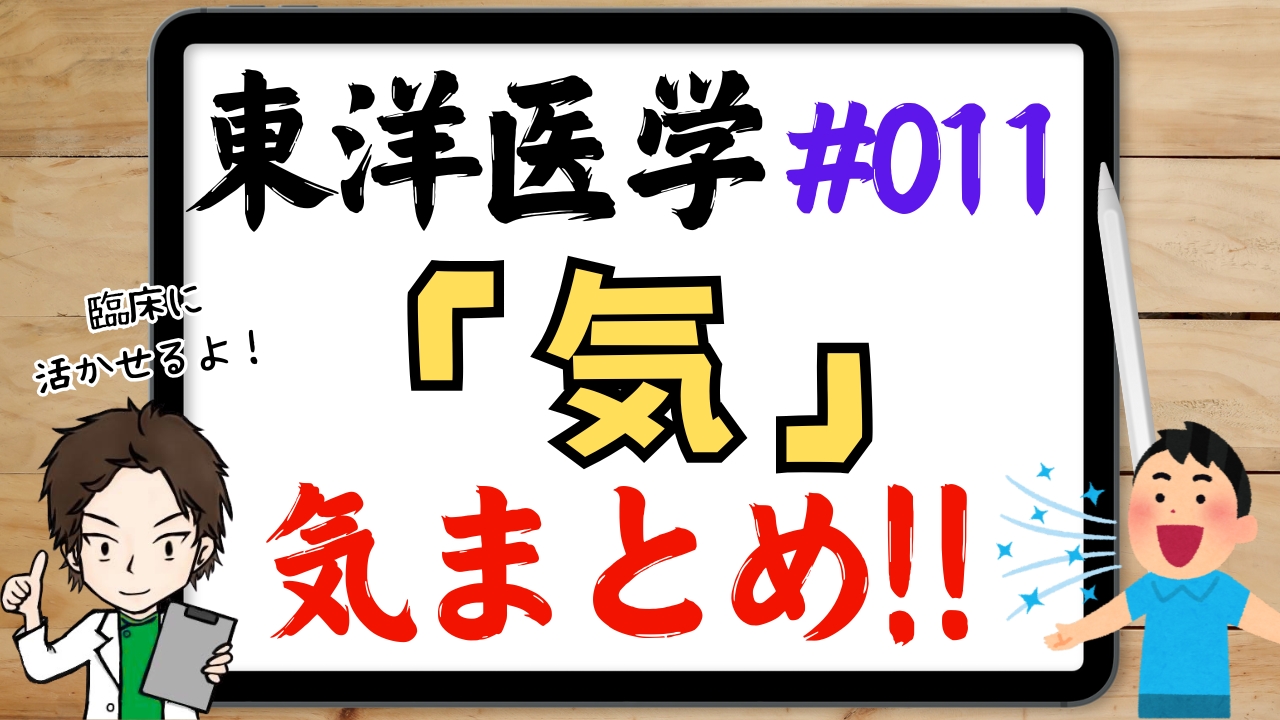
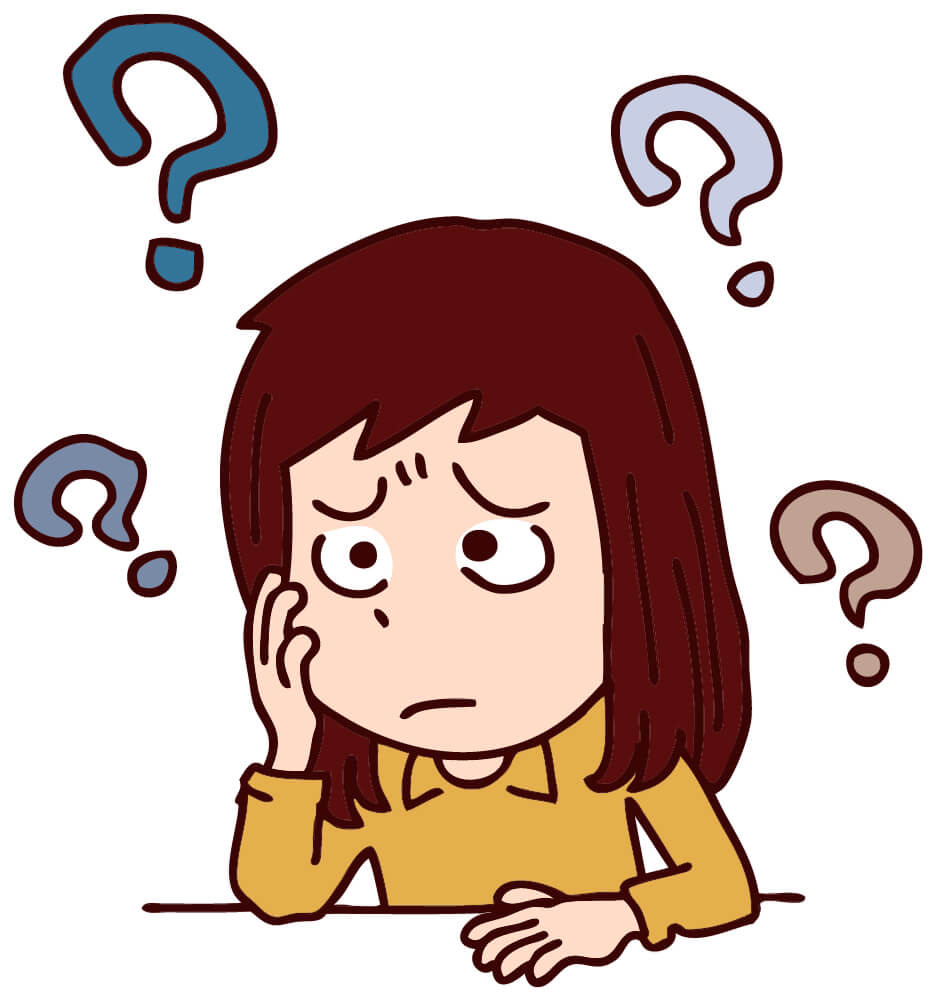

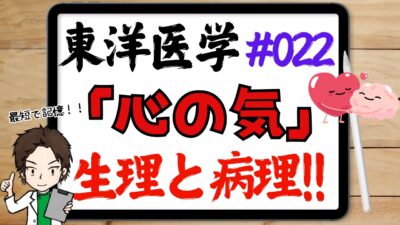

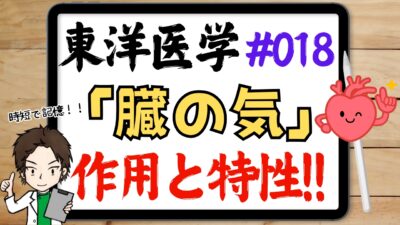
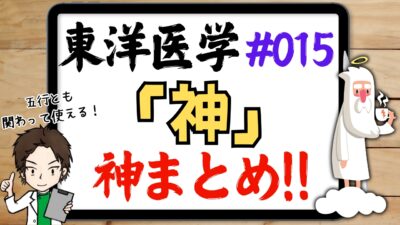
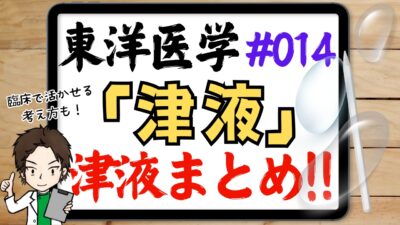
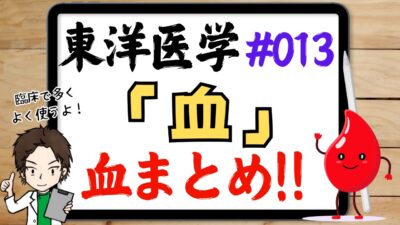
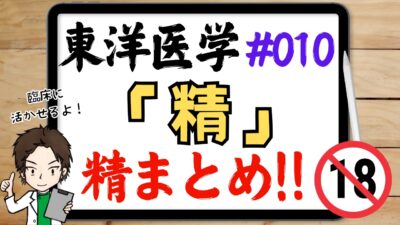
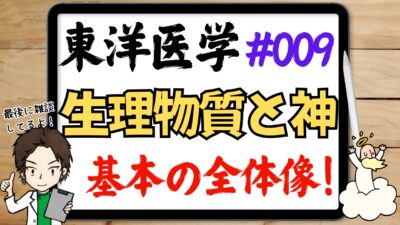
コメント