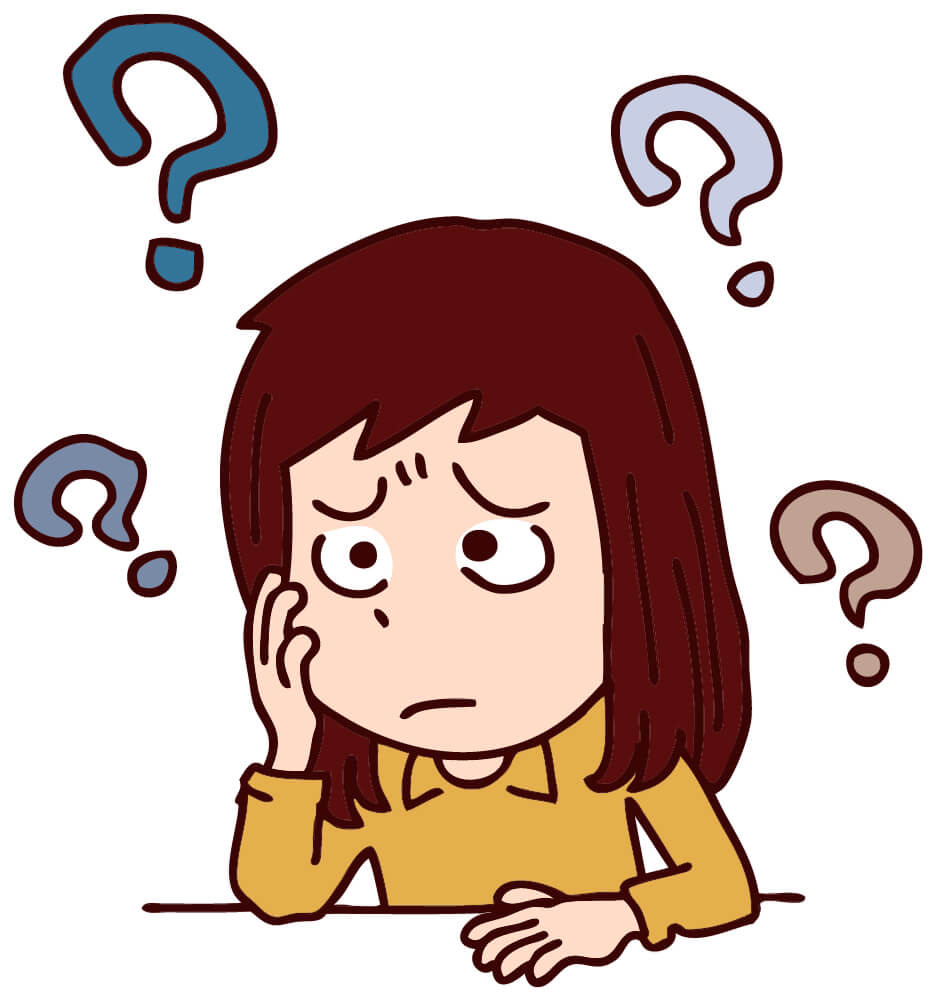 疑問だらけの女性
疑問だらけの女性血って、東洋医学ではどんな働きをするの?
こんな疑問を解消します。
 マッチ
マッチこんにちは、まっちです!
この記事では、YouTubeで解説した「生理物質・血(けつ)」について、国家試験対策として覚えるべきポイントをまとめています。
血は「身体を動かす栄養」と「精神を支える基盤」を同時に担う、非常に重要な生理物質です。
目次
【東概013】生理物質『血』の特徴・作用・病理【国試対策用まとめ】
血とは?(東洋医学)
血(けつ)は、脈内を流れる赤色の栄養液で、組織や臓腑を養い、精神活動(神志)を支えます。
- 臓腑・筋肉・皮膚・感覚器を滋養する
- 精神・思考・意識を安定させる
- 気の推動によって全身を巡る
東洋医学での血は「単なる血液」ではなく、身体と心の栄養源です。
血はどう作られる?(生成)
① 精からの化生
腎に蓄えられた精(腎精)が血に変化します。「精血同源」という超重要キーワードです。
② 飲食物からの化生
- 脾胃:飲食物を消化 → 水穀の精微へ
- 心:血に転化させる(主血)
- 肺:気の推動力で生成を助ける
まとめると、「腎(精)+脾胃(飲食)+心肺(推動)」で血が生まれるということです。
血の働き(作用)
- 滋養作用
全身の組織・器官を養い、健康を維持する - 神志(精神)を安定させる
血が不足すると不眠・健忘・不安が出やすい
血の運行(どう流れる?)
- 心:拍動で全身へ送る(主血)
- 肺:気の働きで推動する
- 肝:蔵血し、必要に応じて放出
- 脾:統血し、血が漏れないようにする
これらのバランスが乱れると、血の病理(血虚・血瘀など)が発生します。
血の病理(試験によく出る)
① 血虚(血が不足)
- 原因:脾虚・出血・過労・飲食不摂
- 症状:顔面蒼白・動悸・眩暈・不眠・健忘
- 肝血虚:しびれ・けいれん・視力低下・爪が割れやすい
② 血瘀(血が滞る)
- 原因:気滞・寒邪・外傷など
- 症状:刺すような痛み・固定痛・瘀斑・舌が暗紫色
- 月経痛(血塊)が国家試験で頻出
③ 血熱(血に熱がこもる)
- 原因:火邪・暑邪・辛いものの過食
- 症状:発赤・発熱・出血傾向・心煩・不眠
④ 血寒(血が冷えて巡らない)
- 原因:寒邪・冷飲食
- 症状:冷え・脈遅・寒による瘀血
血まとめ【無料PDFダウンロード】
YouTubeで使用したスライド資料をPDFとして配布しています。
 ホネ美
ホネ美グッドボタンかコメント忘れんでなー
さいごに
血は身体と精神を支える重要な生理物質です。 試験でも臨床でも必ず使うので、ぜひPDFを保存してご活用ください。
 マッチ
マッチでは素敵なあはきライフを!
あはき整体-治療院


【あはき学生限定】国家試験応援コースのご案内 | あはき整体-治療院
\あはき国家試験を目指す学生さんへ/ 「自分の技術、今どれくらい通用するんだろう…?」「卒業してから後悔したくない…!」 そんな不安や期待を抱える学生さんへ。在学中…
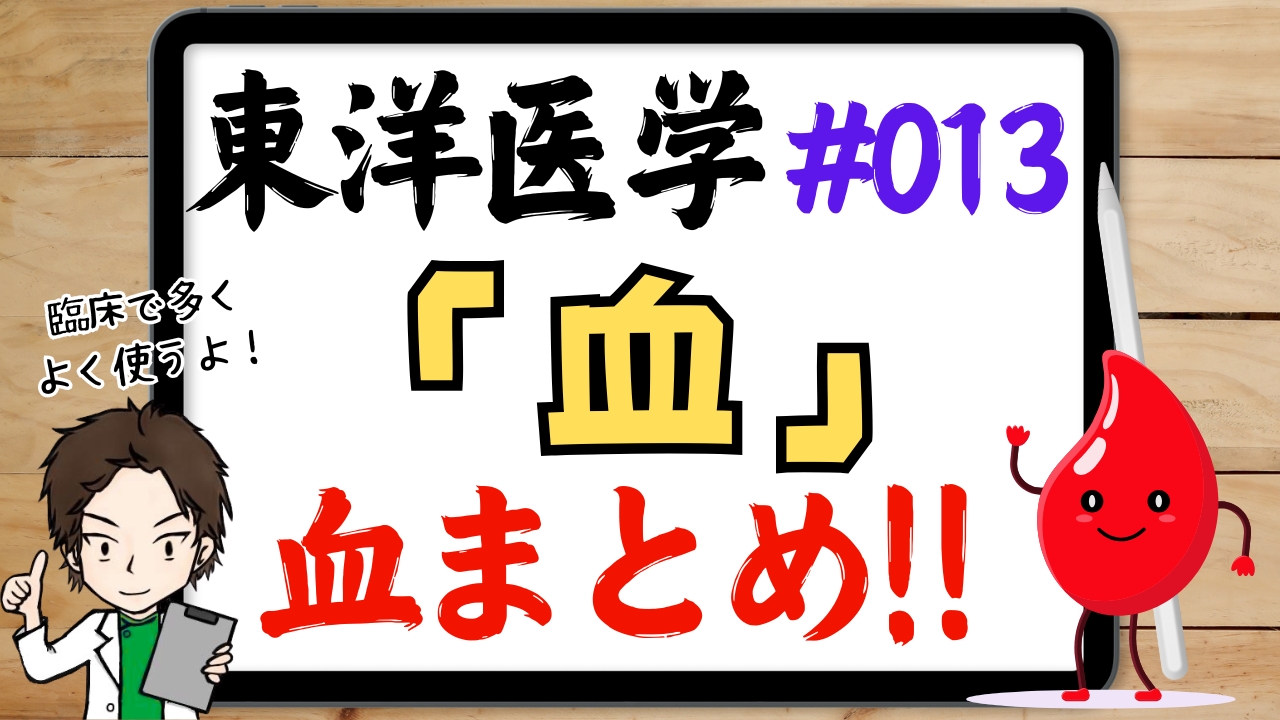
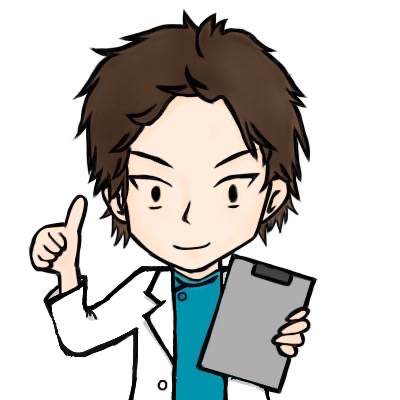
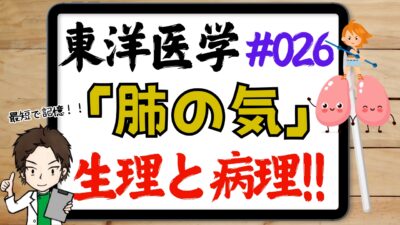
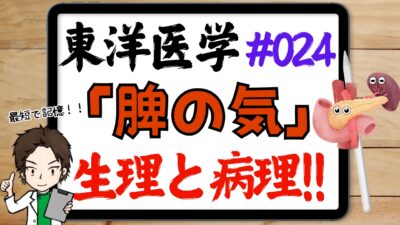
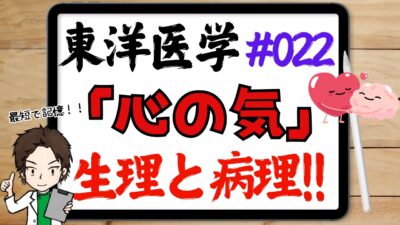

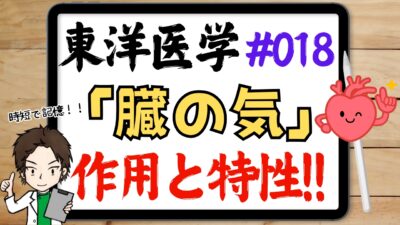
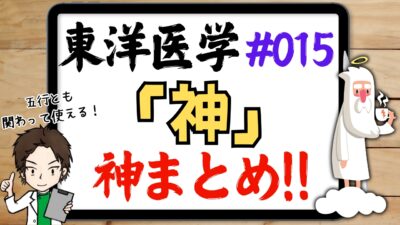
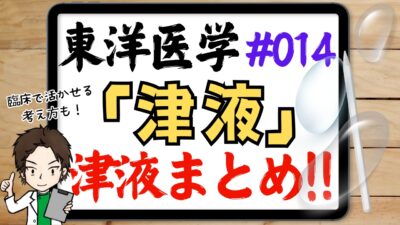
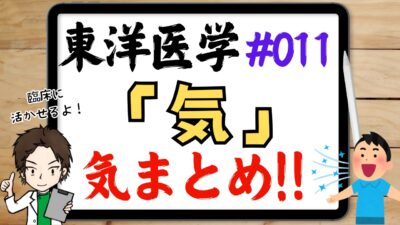
コメント