目次
五行学説とは?【YouTube動画で解説】
五行それぞれの性質
正常な関係:相生と相克
病的な関係:相乗と相侮
 ホネ美
ホネ美YouTube動画でわかりやすく解説してるで。
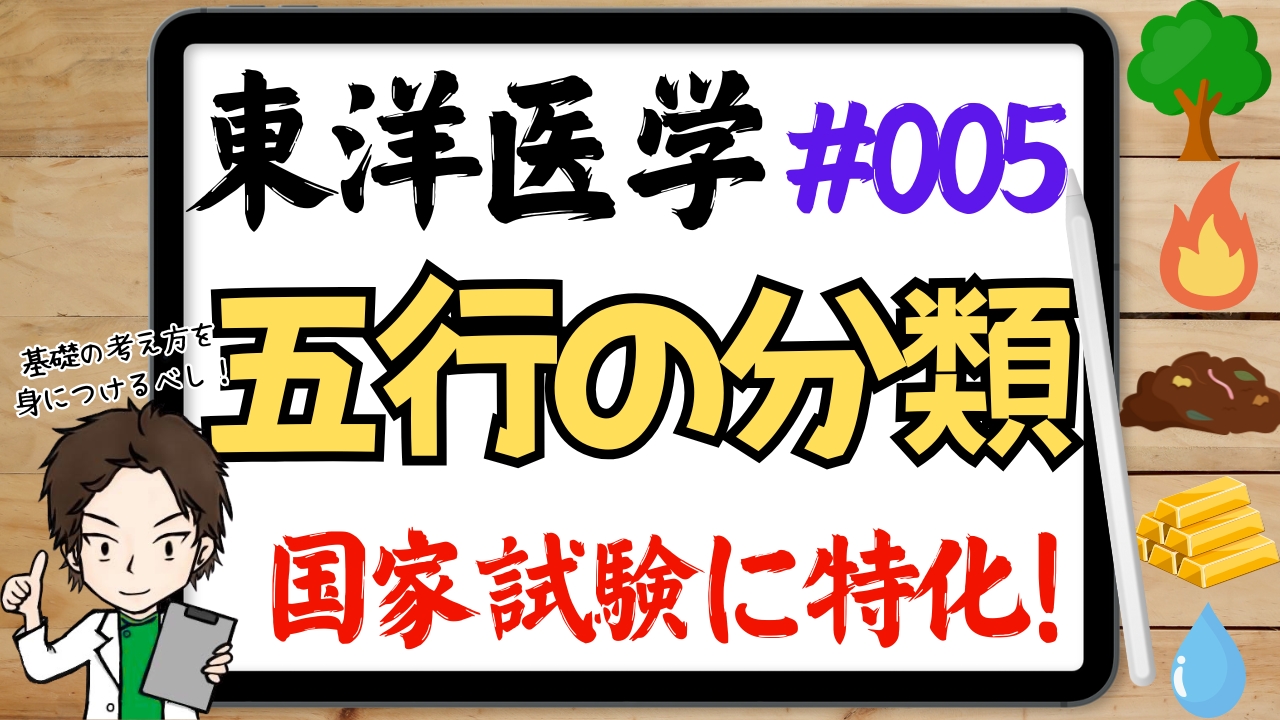
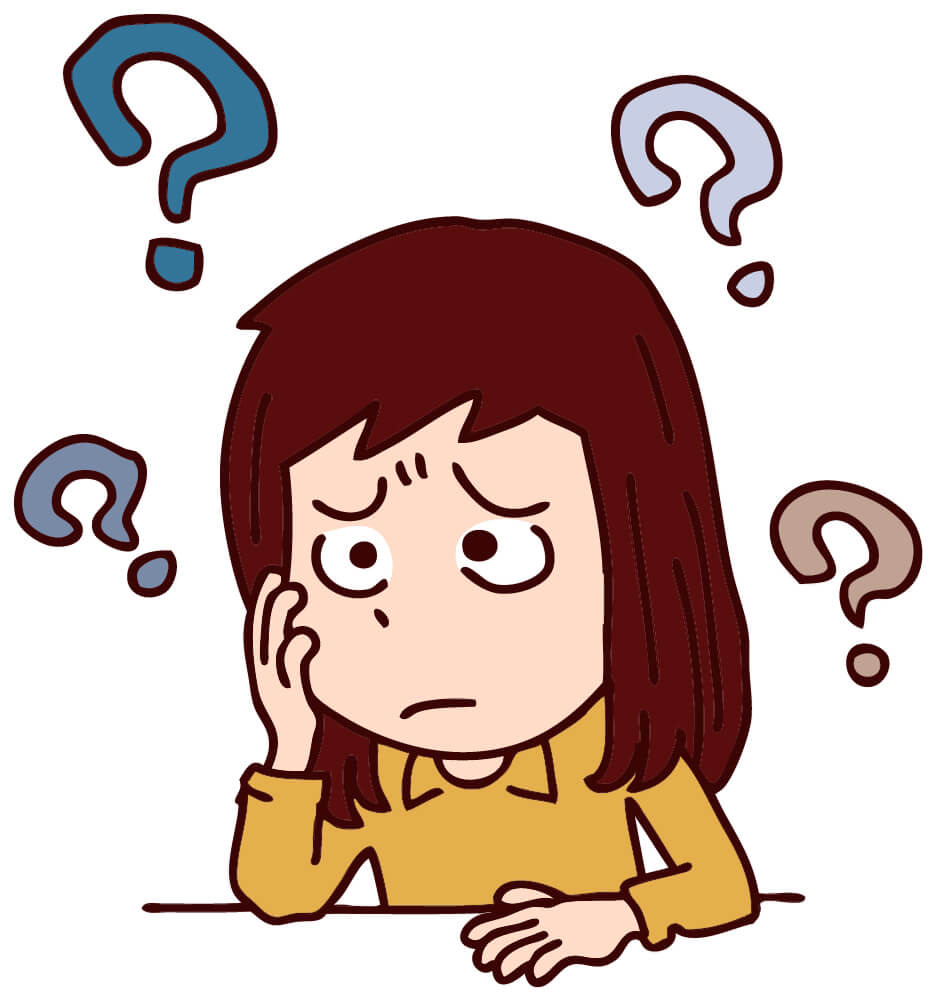 疑問だらけの女性
疑問だらけの女性五行って何?どうやって分類するの?
こんな疑問を解消します。
 マッチ
マッチこんにちは、まっちです!
東洋医学では、自然界や人体のあらゆる働きを「木・火・土・金・水」の5つに分類する【五行学説】を用います。
この記事では、五行学説の基本と、五行の分類についてわかりやすく解説。
さらに、YouTube動画と無料PDFを組み合わせて時短学習するコツもご紹介します!
ぜひ学習に活かしてください。
✔︎【あはき整体ラボ】運営者
✔︎治療家兼実業家
✔︎鍼灸あん摩マッサージ指圧師
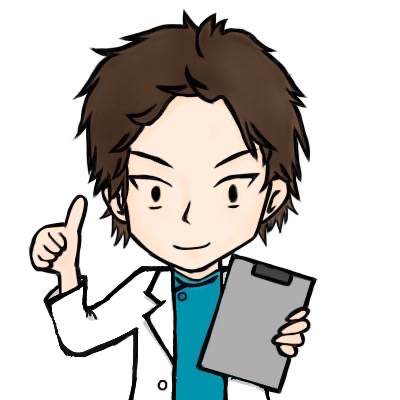
まずは五行学説の全体像をYouTube動画でざっくり理解しましょう。短時間で把握できるので、空き時間や聞き流し学習に最適です。
五行学説では、万物を「木・火・土・金・水」の5つに分け、それぞれが相互に影響し合うことで自然や人体の調和が成り立っていると考えられます。
この学説を理解すると、臓腑の連携や病気のパターンをより深く捉えられるようになります。
次に、五行それぞれの性質と、正常な関係(相生・相克)、病的な関係(相乗・相侮)を見ていきましょう!
それぞれの要素には、伸びる・上昇する・受け入れる・収縮する・潤すなど、はっきりした性質があります。
この性質を人体や自然界に当てはめると、バランスが崩れた際の原因や改善のヒントを得られます。
例として、木生火(木が燃えて火になる)や火生土(火の灰が土を生む)といった「相生」。
一方で木克土(木の根が土を固定する)などが「相克」の代表例です。
この相生・相克のバランスが保たれることで、自然界も人体も健全な状態を維持します。
 ホネ美
ホネ美色々イメージすると理解できるで。
正常な抑制が働かず、力関係が極端に偏ることで、病気や不調の原因となります。
「相生・相克」が崩れて「相乗・相侮」に転じると、臓腑や気血の乱れが生じやすくなるのがポイントです。
 ホネ美
ホネ美YouTube動画でわかりやすく解説してるで。
試験勉強や臨床現場で「五行をパッと確認したい!」という方のために、「五行の分類.pdf」をまとめ直したオリジナル資料を無料配布中です。
五行の性質や相生・相克・相乗・相侮を一覧でチェックできるので、ぜひご活用ください。
五行学説の基本をしっかり押さえると、臨床での東洋医学的アプローチや国家試験対策にも大いに役立ちます。
 ホネ美
ホネ美ダウンロードしたらグッドボタンと拡散ほねがい。
さいごまで記事をお読みいただきありがとうございます。
五行学説は、陰陽学説と並んで東洋医学の土台となる理論です。
ぜひ学校での学びにプラスして、あはき整体ラボ【動画視聴+無料PDFダウンロード】の学習スタイルで、効率的にマスターしてみてください!
 マッチ
マッチでは素敵なあはきライフを!
コメント